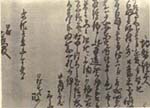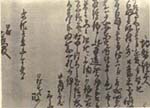宿毛市史【近世編-農村の組織と生活‐土地制度】
田畑に対する制限
農民を農地に結びつけることは、「民を治むる道は土着を本とす」(太宰春台)るにあったが、単に土地に結びつけるだけでなく、それが適正であることを必要とした。従って幕府では寛永20年(1643)に田畑の売買を禁止し、この禁を犯した売主は牢舎の上追放、買主は過怠牢の上その田地は売主の代官または地頭へ取上げ、証人になった者も過怠牢に処すこととした。また質入れも禁止したがこれはいわゆる本田だけで、新田や浪人の田畑は除外しているのをみると、年貢の収納を確保するためであったのである。しかし百姓もみだりに田畑を売る者はないので年貢の不納や生活に窮してよんどころなく売るのであるから処罰は軽くてよくはないかということで寛保2年(1742)には売主は所払、家財は没収には及ばない。死んだ時は子が同罪、買主は過料とする、但しその田畑は取上げ、死んだ時は子が同罪、証人は過料となった。更に延享元年(1744)には売主は過料、加判の名主は役儀取上げ、証人は叱り、買主はその田地没収と改められている。
売買の禁止
土佐藩では寛永の幕府の禁止令より後、寛文10年(1670)に売買を禁止、元禄3年(1690)の大定目では重ねて本田売買の禁止を定めているが、しかし本田の年切売買については「本田の年切売買ならびに地替の儀は代官地頭へ断りをとげ下知にまかすべし」と云って禁止していない。「20年以前に売買した田地は請返すに及ばないが、20年未満の土地は請返すべし。20年をすぎたものも双方が相対にて請返すものは各別の事」としている。「但し近年の売地であってもその田地に買主が大分の造作をしたものは役人へ届けて実情により裁判せしむべし」としているが、田地をみな請返されては渡世の便を失うことにもなるので、双方調査の上半分または三分一を請返し双方渡世のつづくように取計うようにと指示している。(『土佐藩の法制』)
「秋鍬下より以後の証文を以て売買した田地は翌年より買主19ケ年所務せしものは、売渡しの年より20ケ年目の12月限り請地に申しつくべく、翌年正月へ越したるものは流地として取扱うべし」(享保15(1730)年3月20日『御郡方御定目稿』)とあって、土地を質入れしたものが、期限内に支払いができないときは売買が成立したことを認めたことを示すものである。
貸銀米と年限売買はともに担保を設定しての金融方法であるが、(イ)債務者がつづけて耕作するものを貸銀米とし、(ロ)債権者が耕作するかまたはその代行者が耕作するものを売買とする定めであった。(イ)の場合は債務継続期間の利息支払を必要としたので利息を加治子として債権者に支払ったのである。「たとえ加治子米を如何様に相定めるといえども、本銀、本米に定めの利息を加えて返済した時は田地は返すべし」(大定目)とし、延宝2年(1674)の郷中法度には銀の利息は年に1割8分、米は2割5分とするとあるのみで細部に至っては不明である。
「本田を代官給人判形にて買取り候へ共売主が直にアタり作らし候か、或は加治子を引抜買主作らしめ残り地を本主ひかえ候か、又は諸成物諸公事役売主が相勤候においては、すべて貸米の沙汰に候条此度の書付の趣に申付くべき事」(元禄9年子12月1日田地売券御定目書付)とあるのをみると、売買であっても条件によっては貸し銀米の取扱いをするように定めている。また証文の中に20年の間に元金と利息を払ったときは、その土地を請返すと云うものもある。
宿毛市中津野村の土地売渡証文は享保年間から明治に至るもの85通が中村市の郷土資料館にある。その他に有田家文書(弘化5年、1848)の中に庄屋の手扣に残る証文が、90余通と芳奈のものが4、5通発見されている。売渡しの理由としては「年貢未進につき」が多く、また「百姓なり立ちがたく」と云うのは年貢米が納められないものであろう。山の売渡しは少ないがそれでも2、3はある。当時山は所有権がなかったのであるが、薪などある程度の山の支配は認められていたものと思われる。田畑の売買でもその大半は1反以下であるのでその為に百姓を転落したとは考えられない。しかし有田家文書は手扣であって、その理由なども書かれていないものが多いが、その一部を表にして次に揚げる。安東(伊賀)家或は家来の領知を売っている例もある。広瀬様御知行所、安東様御分とあるところをみると耕作権の売買であったことが明らかである。これは明治5年に地券を発行して所有権を耕作者に認めるまで続いたものであろう。
| ホノギ |
田 地 |
貢 物 |
代 金 |
所 有 |
売 主 |
年 月 |
願成寺□ノ内
アタゴリヨ
カチヤカ市
谷川口
そいの西
高ぞり谷川口
船谷
キウセンデン
ミノコシ
八 番
二十三番
八 番
九 番
四十五番
四十六番
小田方
三百石分ノ内 |
壱畝二歩
九畝歩
五畝
中地三畝
田中地八畝二歩
小地一畝十歩
中地五畝
田畑弐反五畝
畑十四歩
名地十石ノ内
同七石五斗
同三石五斗
同十石
同五石
同十石
同五石
同十石
畑荒二畝十四歩
|
加治子三升
御見立
御見立
御見立
一斗七升五合
三升
九升
四斗ノ筈
七合五勺
|
三十八匁六分四厘
三石七斗七升
一石五斗
太一石二斗
六斗
二石
三升
二石
一石五斗
五石三斗
二石
一石
二石
太米八升
|
竹内分
妙栄寺分
右の寺分
新倉分
横山権太夫
安東様小地
御蔵入
広瀬様御知行所
浜田御上知
七石五斗
二石五斗
時岡御分
広瀬御分
広瀬御分
広瀬様御分
|
市助
吉之進
吉之進
和田村恵八
和田村浅七
伊之助
新蔵(親類ノ儀ニ付証文受取不申候)
与八
久米七
宅蔵
五平
平蔵
藤蔵
親・友七扣
右同断
御家来竹蔵
宿毛御家中岡
添太市左衛門 |
文政八酉年三月
文政元寅年三月八日
文化四卯年三月四日
天保六未年十二月
文化十酉年十二月十四日
文政元寅年十二月十一日
文政四巳年十二月
文政五午年十二月
天保四巳年春
天保七申年十二月
嘉永七寅年九月
|
右の中で「年貢御見立」というのはいわゆる新田のうちであろうが、年々毛見の上決定されたものであろうか。ここでもまた、くじ地であると思われる御蔵入として名地の売買がなされているが、八番十石のうち七石五斗と二石五斗で2人の売主が書かれているし、三石五斗というように売られているものがある。最後の岡添太市左衛門は郷士であったものであろうか。「三百石分のうち」というのはどういうことを意味しているのか不明である。
 | 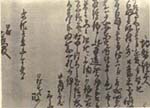 |
| 田地売買扣 | 地替証文 |
中角村の証文のうち「永代売り」と「年数売り」の証文を掲げておく。
永代売渡証文
藤好上知
一名地六石三斗一升一合也
但名入小地高共、代米十一石六斗一升一合四勺
-
| 右は当年御貢物難催ニ相成候ニ付達々及御相談右の名地名入小地共永代売渡代米慥受取申候処相違無御座候、右の名地御勝手次第御作配可被下候、此地ニ付御公向ハ不及申上其外村中類中何等の相障ル儀無御座候、為其御庄屋老所奥書加判請井二受人相立申上ハ少茂違乱無御座候、仍而永代売渡証文如件
|
天保九年戌十二月廿二日
売主 喜六
受人 銀蔵
清助殿
前書通り相違無御座候以上
中角村庄屋 平次衛門
同 村 老 友 七
年数売渡証文
御蔵入分わらひ□ニ有
1.小地二畝
代米一石二斗
-
| 右は私儀無拠入用之儀御座候ニ付達々及御相談右は本申年より巳の年迄年数十ケ年売渡候代米慥ニ受取申候処相違無御座候、年数ノ内1割加地子米相立私作付可仕候、年明時ハ元米ヲ以御かへし可被下候、若請米相滞候時ハ永代相渡可申候、右之小地ニ付御公義向ハ不及申上其外村中類中何等之相障ル義無御座候、為其御庄屋老配中奥書加判受井ニ請人相立申上ハ少茂違乱無御座候、仍而年数売渡証文如件
|
天保六未年十二月
売主 二宮村 清蔵
受人 同 村 貞助
清助殿
 |
| 売渡証文 |
これら中角村の証文は幕末頃のものが多く、85通のうちの買主は清助が32件、所平15件、六右衛門14件、善平8件であっていずれも庄屋である。これでみると地主化の傾向が明らかで、村役人のところへ集中されて行ったものと考えられる。
分地の制限
本田畑の売買は禁制であったが子供や由緒ある者への譲渡は許されていた。しかしそのため百姓の持高が減少して零細化することは担税能力の低下を来すものとして一定規模以下の分割は禁止されている。寛文13年(1673)に名主は高二十石以上、百姓は十石以上の者でなけれは分割を禁止し、正徳3年(1713)にはこれを強化して、残置、分割ともに高十石、反別にして一町以上とした。その後一時ゆるやかになったが、宝暦9年(1759)には旧に復して結局高二十石、二町歩以内は分割が禁止された。(『地租改正』)
「親の田地高十石、内反別一町歩より内は兄弟に分け譲らせまじく、弟は奉公に出るか養子に遣すか、兄と一緒に居て田畑を作り万事を稼ぎ又は職人にもすべし。十石一町より少しにて分くるときは段々小高になり末には水呑同然と成て互に苦しむ、これをわけるを古来より田分(たわけ)と云ひて馬鹿にたとへたり」(『地方凡例録』)とあって分地して小農となることを極端に制限している。
しかし何事にも脱法手段はある。家抱(けほう)、分附(ぶんづけ)という隷属的な身分関係を設定して実質上は小高の土地を分与する方法である。幕末の慣行では「若し十石以下の分地を受ける者は百姓の名跡なく誰の門屋(かどや)と称して多少権利の劣る者とする」(飛弾大野郡)としているところもある。「分家するものは高十石以上所持の者に非ざれば許可なきの定例なれども町村吏限り別籍を許すもの多く終には分家同様混淆せるもの多き慣習なり」(肥後天草郡)というのが一般的だったのであろう。一方領主は戸数の増加に留意して「分家増殖するときは官より賞与の典ある法なり」とするものもあった。「役場において黙許し分家せし者は宗門改のとき戸数の増す事を屈け出づ」とあって、検地帳と宗門人別帳との間に戸の違いを生ずる。傍系血族や名主層の独立がこのようにしてみられる例もあった。(『地租改正』)