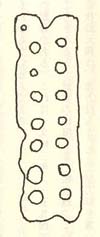宿毛市史【古代編-平安時代の宿毛-】
古代、中世の沖の島
 |
| 沖の島全景 |
沖の島に人が住み着いたのはいつであるか、これをはっきり物語る史料はない。しかし、多分に伝説的ではあるが島の開発について3つの説が伝えられている。
妹背島伝説
土佐国の妹兄知らざる島に行きて住む話
今は昔、土佐国幡多郡に住みける下衆ありけり。おのが住む浦にはあらで他の浦に田を作りけるに、己が住む浦に種をまきて、苗代と云ふことをして殖うべき程になりぬれば、その苗を船に引入れて殖人など雇ひ具して、食物より始めて馬歯うまぐわ、辛鋤からすき、鎌、鍬、斧、鐺たつぎなど云う物に至るまで、家の具を船に取り入れて渡りけるにや、14、5歳許りある男子、そが弟にて12、3歳許りある女子と、2人の子を船に守り目におきて、父母は殖女雇ひ乗せむと陸にのぼりにけり。
あからさまと思ひて船をば少し引きゐて綱をば捨ておきたりけるに、この2人の童部は船底により臥したりけるが、2人ながら寝入りにけり。その間に塩満ちにければ船は浮きたりけるを、放つ風に少し吹き出されたりける程にて、塩干にひかれて、はるかに南の澳に出でけり。澳に出でにければ、いよいよ風に吹かれて帆上げたる様にて行く。その時に童部驚きてみるに、かかりたる方にもなき澳に出でにければ、泣き迷へどもすべきようもなくて、たヾ吹かれてゆきけり。父母は殖女をも雇ひ得ずして、船に乗らむとて来てみるに船もなし。しばしは風かくれに差しかくれたるかと思ひて、と走りかく走り呼べども誰かは答へむとする。返す返す求めさわげども跡形もなければ、いふかひなくて止みにけり。
然てその船をばはるかに南の沖にありける島に吹きつけにけり。童部おつおつ陸に下りて船をつなぎてみれば、あへて人なし。返るべき様もなければ2人泣きゐたれどもかひなくて、女子の云はく「今はすべき様なし。然りとて命をすつべきにあらず、この食物のあらむ限りこそ少しづつも食ひて命をも助けめ、これが失せはてなむ後はいかにして命は生くべき。然ればいざこの苗の乾かぬ前に殖ゑむ」と。男子「ただいかにもして汝が云ふに随がはむ、現に然るべきことなり」とて、水のありける所の田に作りつべきぞ求め出して、鋤鍬などみなありければ、苗の有りける限り皆殖ゑてけり。然て鐺たづきなどありければ、木伐りて庵など造りて居たりけるに、生物なりものの木時に随ひて多かりければ、それを取り食ひつつ明し暮すはどに秋にもなりにけり。
然るべきにやありけむ、作りたる田いとよく出で来りければ。多く刈りおきて妹兄いもせすごす程に、漸く年頃になりぬれば、さりとてきにやあるべき事にあらねば妹兄夫婦いもせめおとになりぬ。しかし年来としごろをへる程に男子女子あたま産みつづけて、それを亦夫妻めおととなしつ。大きなる島なりければ田多く作りひろげて、その妹兄が産みつづけたりける孫の、島に余るばかりなりてぞ。今にあるなる。土佐国の南の沖にの島とてありとぞ人語りし。これ思ふに、前世の宿世によればこそは、その島にも行き住み、妹兄も夫妻ともなりけめなむと、語り伝へたるとや。(今昔物語巻第26)
今もこの曇中央の高い山を妹兄山といっているので、恐らく、ここにいう「妹兄島」とは、この沖の島のことに間違いなかろう。
母島の開発
母島の開発については、沢近文書の『御境目由来書』によると、『沖の島は、昔人が住んでいなかったのであるが、大峯(大和の大峯か)から山伏が渡って来て、芦のおりのりへ船を着け、尻なし尾を登って、峯伝いに鍬抜の峠まで通り、それから川へ下って母島に住居した。沖の島のでき始めの浦であるので、母島と名付けた。その頃は、母島浦に、善福寺、寿生庵、幸禅庵、清蔵庵、旨定庵、出心庵、峯伝庵という7つの寺があった。その後、我等の先祖が流人であったが、この島へ渡り、住居して数十代になる」とある。
弘瀬の島祖三浦則久
沖の島弘瀬の島祖については、次のような物語が伝わっている。
鎌倉幕府の重臣であった三浦大助の孫に、三浦新助則久という人がいた。何かの事情で罪を受けたのか、その家族家来ともども西へ西へと逃れたのであった。伊予の三津浜から、更に船出して沖の島に着き、芦のおりのりから上陸したのであった。そして、峯伝いに島を縦断して仏の峠(弘瀬と谷尻間の峠)に居を定め、その付近を開墾して農耕をなし、海岸に出ては漁業をして生活を始めたのである。
この地には、御先祖様といわれる数十基の石碑が林立し、三浦家と、仏の峠の歴史の古さを物語っている。
三浦家の先祖を祭った神社を若宮神社といい、荒倉神社の境内にあるが、その御神体として三浦氏先祖の鎧を祭っている。しかし、その鎧は、江戸初期前後の具足で、古いものではないが、その鎧を入れた箱の中に、わずか2片ではあるが、皮製の古い小札こざねが入っていた。この小札こそ古い鎧の残片である。その小札の写真、実測図を山上八郎氏に見せたところ、伊予札いよざねで南北朝時代のものであろうということであった。これが、三浦家の古さを実証する1つの資料である。新助則久から8代まで仏の峠に居り、9代目から弘瀬に居住し、島の領主として村君むらきみを勤めていたのである。
 |
 |
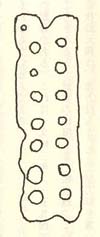 |
| 三浦家の具足 |
三浦家の鎧の小札 |
三浦家の鎧の小札
実測図(原寸大) |
村君、三浦氏
村君むらきみとは、室町時代の浦の領主的な存在で、後の庄屋以上の大きな権限をもっていたようである。
弘瀬浦の村君であった三浦宗見の証文には、7か所も村君の事が記されている。
-
| ○ | むろ網で、魚がどれほどとれても、村キミが3分の1はとること。 |
| ○ | 千州より借りた家敷の借り賃200文は、村キミが調へ、後で一軒につき50文ずつ村キミが取ること。 |
| ○ | 地下へ流れ寄ったものは、地下の者が拾っても村キミが取ること。 |
| ○ | 引猟で、どれほどとれても、半分は村キミが取ること。 |
| ○ | 土地を出て行く者の網や船も、村キミの身代とすること。 |
| ○ | 正月1日、3月3日、5月5日、7月15日に地下中を集めて酒で祝をするのは、村キミの用事のため、いつ使うかもわからないからである。 |
などの記録がある。これは、文禄3年(1594)のものであるが、室町末期には、まだこのような証文が残っているところをみると、村君の権限もまだ相当残っていたことと思われる。
長宗我部元親は、地方役人として庄屋刀祢を置いたが、弘瀬の刀祢は三浦助左衛門を任命しているので、村君をそのまま刀祢としたことがわかる。
入相地と国境
元々、沖の島の中に、国境などはなかったのである。この小さな島で、伊予、土佐両国に分かれて、生活に便利なはずがない。それで、島も海も境は無く、木を切っても漁をしても自由に行われていたのである。
それが、土佐側の勢力が、柏島を経て沖の島の弘瀬に及び、一方伊予の御荘の勢力が鵜来島に至り、室町時代には既に伊予土佐両国に2分されていたのである。
元々、境の無い所に、人為的に境を引いたため、島民は、それまでのしきたりを続け、海、山ともに双方が入りあって採取する、いわゆる入相が行われていたのである。例をあげると、伊予領の大和おおわ山へは柏島から木を切りに行き、土佐領の長浜沖や、姫島の南のはなへは伊予領から漁に出、白岩岬から児島までは土佐から漁に行くといった調子であった。
戦国時代になると、幡多郡は一条氏が領し、伊予の御荘は御荘勧修寺氏が領していた。そのため、土佐領沖の島は一条氏、伊予領沖の島は御荘勧修寺氏の領地であった。
土佐領は天正3年以後は、長宗我部氏、伊子領は天正15年戸田民部の領地となった。
長宗我部元親が戸田民部に、朝鮮在陣の時、相談して予州分の弘瀬を借りたのであるが、これら入相地、借り地が、後年大きな争いの元となったのである。このことは近世編の沖の島国境争いの項で詳しく述べることにする。