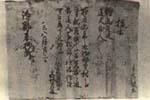|
| 田役普請 |
享保4年(1719)12月24日「幡多郡村々田役御普請所願目録」には中山善左衛門、矢野川瀬介、矢野権兵衛、永尾源七、重松所兵衛、野口功平、岩崎伝六、前田平蔵」の連名の表紙があり、享保6年丑の指出には「今春私共支配の田役方え貴様御越なされ毎々屹度仰せつけられ御普請所御積り帳に引合せ1ヶ所も残し置かず丈夫に相調へ申すところ相違御座なく候。尤貴様御儀は村改御支配なさるわけに御座候へぱ如終1ヶ村ニ御詰なさる儀にはなリがたき段私ども百姓は扣地に応じ甲乙なき割合を以て日々夫使い申候、別して御普請所残しおき申し又ハ粗相に仕る筋など致しおき重ねて相願申候はゞ如何様とも仰せつけらるべく候」とあり「出井村庄屋岡村儀右衛門、同村年寄源作、楠山村庄屋篠田三良兵衛、奥屋内村庄屋六左衛門、同村年寄茂兵衛」とあるが、それ以下の人々の名は判読できない
別の一紙には「享保6年丑ノ春私ども支配の村田役仕り候、普請所1ヶ所も残らず田役夫御積りの通り悉□□□被仰付候ところ相違御座なく候、其節何の依怙ひいき並びに親類がましき儀少しも御座なく候。もし御普請所粗相ニ仕り何辺によらず申分これあり候得ば只今申し出候えと仰せつけられ其段小百姓に至る迄委細申し聞せ候へども何の申立も御座なく候。其ため庄屋年寄連判仕る上は後日に何の申し分も御座なく候。享保6年丑ノ3月6日、楠山村庄屋篠田三郎左衛門、同村老年寄忠三郎」とあり田役御役人宛に差出されたものであろう。前の願は田役終了の報告書と思われる。
これと共に宿毛市小筑紫町の一部の田役夫の記録があるので次に掲出する。さきに出した「明暦元年より田役と申候、一町に三十人宛」とあるのに符合するものである。
一、地二百八十九石三斗三升一合 福良村本田
内 五十一石八斗七升四合 荒
十五石 庄屋小遣直地
〆六十六石八斗七升四合 万引地
〆二百二十二石四斗五升七合
此夫六百六十七人四歩 但一石に三人
加夫 二十人二歩 九歩増役
〆
一、積夫千二百九十人一歩
内 八百七十六人三歩 右所有夫
四百十三人八歩 至極不足夫
(この古文書は順序がバラバラになっているのであるが、一石に三人役、九歩増役と合計したものが積夫で、そのうちこの村の人夫と不足の人夫の数が記されている。)
右の目録は「享保5年子ノ正月9日に中村御会所にて写す」とあり、享保4年から6年の分が入りまじっているが、「幡多郡村々田役御普請願」による村々の課役を示すものと考えられる。これはまとまったものでなく宿毛市の一部分ではあるが、本田新田を含めて、一石につき三人役であり、九歩増役をも必要としたようである。土佐来集には百姓役について「用水溝さらへ、川除等のため田役と申し本田一反につき一ヶ年に三人役づつ勤め申候、右のうち田役夫に不足仕る普請は上より飯米つかわされ、または押し立たる破損は日用普請なさるべく候」とある。