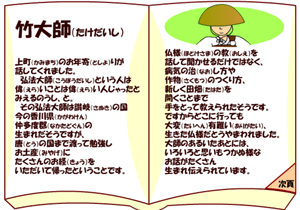
上町のお年寄りが話してくれました。
弘法大師(こうほうだいし)という人は偉いことは偉い人じゃったとみえるのうし、と。
その弘法大師は讃岐(さぬき)の国、今の香川県仲多度郡(なかたどぐん)の生まれだそうですが、唐の国まで渡って勉強し、お土産にたくさんのお経をいただいて帰ったということです。
仏様の教えを話して聞かせるだけではなく、病気の治し方や、作物の作り方、新しく田畑を開くことまで 手をとって教えられたそうです。
ですからそこに行っても大変有難い生きた仏様だとうやまわれました。大師のあるいた後には、いろいろと思いもつかぬ様なお話がたくさん生まれ伝えられています。
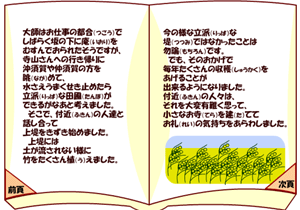
大師はお仕事の都合で、しばらくの坂の下に庵(いおり)をむすんでおられたそうですが、寺山さんへの行き帰りに 沖須賀や仲須賀の方を眺めて、水さえうまくせき止めたら立派な田圃(たんぼ)ができるがなあと考えました。
そこで、付近の人達と話し合って、上堤をきずき始めました。上堤には、土が流されない様に竹をたくさん植えました。
今の様な立派な堤(つつみ)ではなかったことは勿論です。
でも、そのおかげで毎年たくさんの収穫をあげることが出来るようになりました。付近の人々は、それを大変有難く思って、小さなお寺を建ててお礼の気持ちをあらわしました。
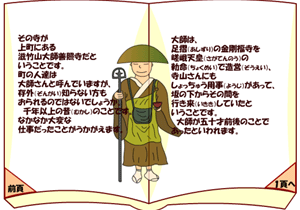
その寺が上町にある渋竹山大師善照寺だということです。
町の人達は大師さんと呼んでいますが、存外(ぞんがい)知らない方もおられるのではないでしょうか。
千年以上の昔のことです。なかなか大変な仕事だったことがうかがえます。
大師は、足摺(あしずり)の金剛福寺(こんごうふくじ)を嵯峨天皇(さがてんのう)の勅命(ちょくめい)で造営、 寺山さんにもしょっちゅう用事があって、坂の下からその間を行き来していたということです。
大師が五十才前後のことであったといわれます。


