
千年もあまりも昔のことでした。
平安文化の花もひらき、海外との往来(おうらい)が始まっていました。
しかし、そのかげでは、みやこ人たちのみにくい政争(せいそう)がくりひろげられておりました。

昌泰(しょうたい)四年(901年)の春がようやく訪れようとするころ、
時の左大臣(さだいじん)藤原時平(ふじわらのときひら)たちの暗躍(あんやく)によって、菅原道真(すがわらのみちざね)は 右大臣(うだいじん)の職をおわれ、
太宰権帥(だざいのごんのそち) という低い身分におとされました。

そのため、都をはなれてはるばると筑紫(つくし)の国、九州大宰府(きゅうしゅうだざいふ)まで出むかなければならなくなったのです。
長男・高視(たかみ)も高知の潮江(うしおえ)におわれ、親子がともどもに都をはなれて暮らさなければならなくなりました。

道真は都でも指折りの仕事のできる人でしたが、時平達はそれをねたんで、理由をかまえて親子ともども遠国(えんごく) においやってしまうようにしたのでしょう。
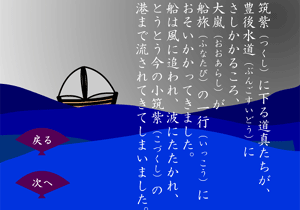
筑紫に下る道真たちが、豊後水道にさしかかるころ、大嵐が船旅の一行(いっこう)におそいかかってきました。
船は風に追われ、波にたたかれ、とうとう今の小筑紫(こづくし)の港まで流されてきてしまいました。

それでも、無事に陸地に着くことのできたことを一同喜び合い、港の中の小高い島にのぼりました。
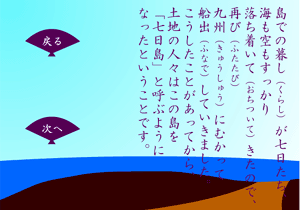
島での暮らしが七日たち、海も空もすっかり落ち着いてきたので、再び九州にむかって船出していきました。
こうしたことがあってから、土地の人々はこの島を「七日島(なぬかじま)」と呼ぶようになったということです。

そのとき道真は、はるばると長い旅路(たびじ)を続けてきたので、もう筑紫の国に足がけしているのだろうかと思ったのでしょう。
「ここも筑紫か。」と、供の人々にたずねました。
その道真の気持ちをのちのちの人々がおしはかってのことでしょう。
この地を、小さな筑紫、「小筑紫(こづくし)」と呼ぶようにしたということです。


