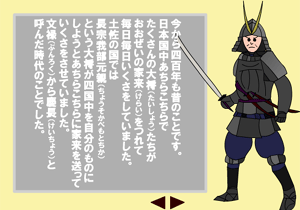
今から400年も昔のことです。
日本国中あちらこちらで、たくさんの大将たちが、大勢の家来をつれて毎日毎日戦をしていました。
土佐の国では長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)という大将が四国中を自分のものにしようとあちらこちらに 家来を送って戦(いくさ)をさせていました。
文禄から慶長と呼んだ時代のことでした。
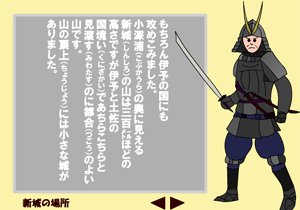
もちろん伊予の国にも攻め込みました。
小深浦(こぶかうら)の奥に見える新城の山は、三百メートルほどの高さですが、伊予と土佐の国境いであちらこちらと見渡すのに都合のよい山です。
山の頂上には小さな城がありました。

小さな城でもそれはそれは苦労してきずかれました。お年寄りたちが、どうしてあんな大きな石をうごかしたのかと首をひねりながらいろいろ話をしてくれました。
そんな石もほとんど落葉でうまってしまいました。四百年もすぎたのですから無理もないことです。
その城から家来たちは山や谷をつたって、あちらこちらと戦をしてはかえってくるのです。

とりたてるほどの高い山はなくても、茂った山々の中です。途中で傷ついたりたおれたりして、帰ってくることのできなくなった家来もたくさんありました。
そのうち城はやけおちてしまいました。城の大将は家来をつれて山をおりました。
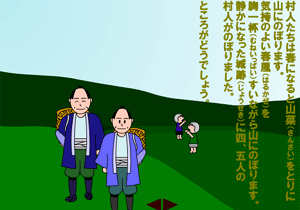
村人たちは春になると山菜をとりに山にのぼります。気持ちのよい春風を、胸いっぱいすいながら山にのぼります。
静かになった城跡に四、五人の村人がのぼりました。
ところがどうでしょう。
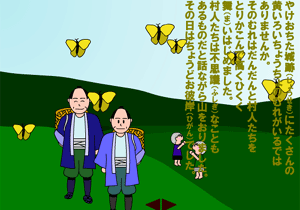
やけおちた城跡に、たくさんの黄色いちょうちょのむれがいるではありませんか。
そのむれはだんだんと村人たちをとりかこんで高く低く舞いはじめました。村人たちは不思議なこともあるものだと話しながら山をおりました。
その日はちょうどお彼岸(ひがん)でした。

よく年の春になって村人たちは新城のちょうのことを思い出しました。同じようにお彼岸にのぼってみました。
今年もちょうのむれは、うれしそうに近づいてきました。去年と同じように自分たちのまわりをむれ飛ぶちょうの姿を見て、これはきっと戦死した兵隊たちのたましいが姿を変えてあつまってくるのだろう、と話しあいました。
お彼岸がすぎてのぼっても、ちっとも黄色いちょうちょに会うことはできませんでした。

明治の終わりころまで、お彼岸に城跡にのぼると必ず会うことができたということです。
一年に一度だけ、こうしてであっていろいろなことを話し合い、なぐさめ合っていたのでしょう。


